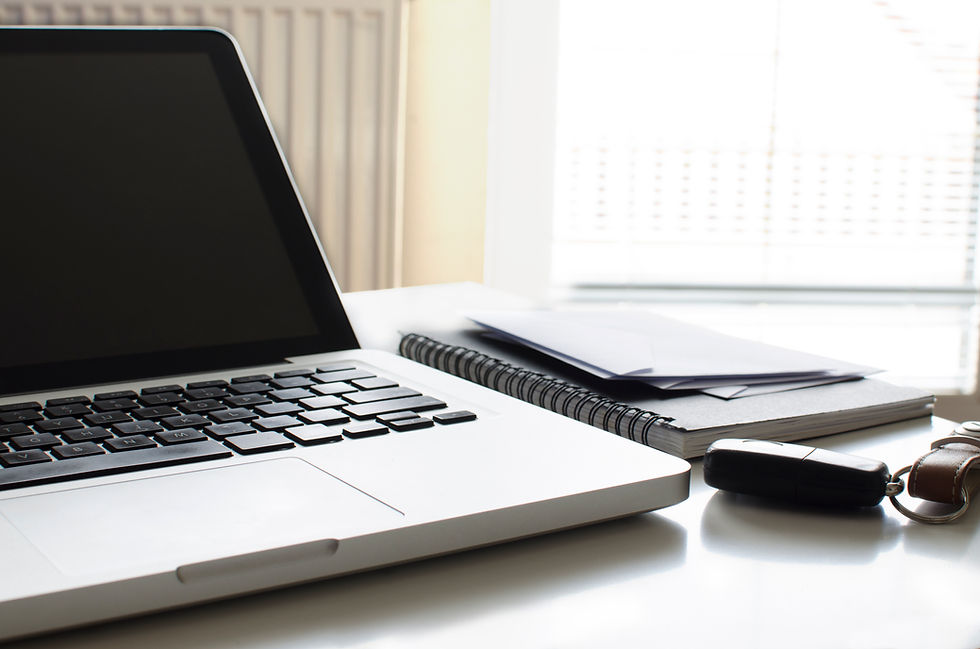英作文の採点基準を徹底解説!内容、構成、語彙、文法のポイントとは?
- Manami
- Oct 26, 2024
- 5 min read
Updated: Nov 19, 2024
英語学習者や留学生にとって、英作文はスキルを測る重要な指標の一つです。英検をはじめとしたIELTSやTOEFLでも英作文はありますよね。英作文の採点は、単に文法やスペルの正確さをチェックするだけでなく、内容、構成、語彙、文法の4つの基準に基づいて評価されます。この記事では、それぞれの採点基準について詳しく解説し、効果的な英作文の方法を紹介しますね。アメリカでの駐在や在住、留学生の皆さんにも役立てたらと思います。
記事内容:
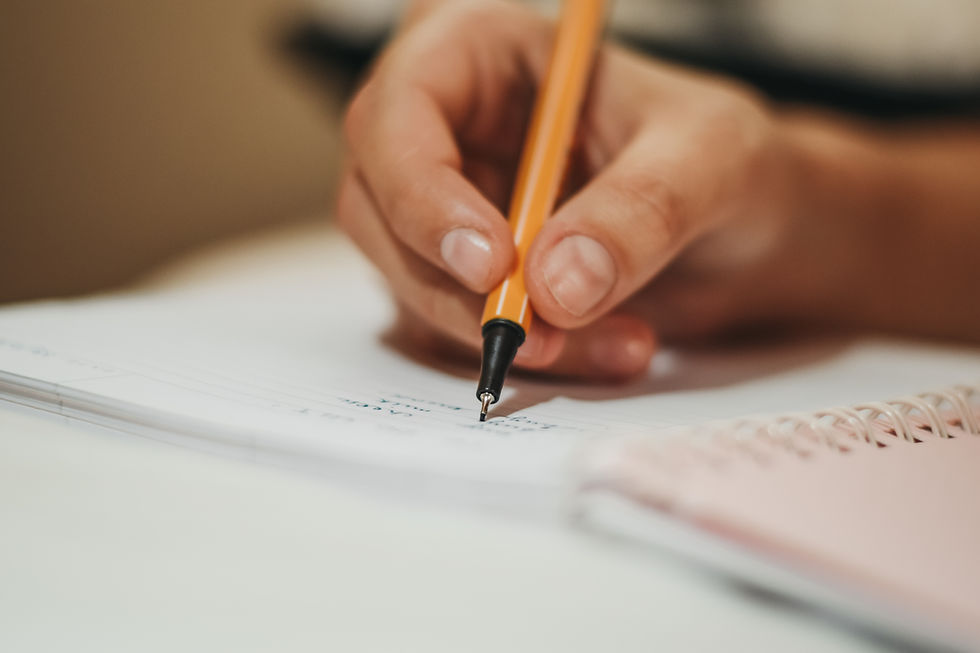
1. 内容(Content)
英作文の内容評価は、主に以下の点に基づいて行われます:
課題の理解度:課題に対する理解が示されているか。問題に対して的確に答えているかどうかが重視されます。例えば、「アメリカの大学生活の良さについて書きなさい」という課題が出された場合、留学生としての視点を含めながら、自身の経験や具体例を挙げることで高評価が期待できます。
アイデアの深さと独自性:単に表面的な意見だけでなく、深い考察や独自の視点が含まれているかが評価のポイントです。論理的な根拠を持った意見を展開することが求められます。アメリカの駐在経験や在住中に得た知識や視点を盛り込むと、より説得力のある内容になるでしょう。
具体例の使用:説得力のある文章にするためには、具体的な事例を挙げることが重要です。抽象的な議論に終わらず、具体的なエピソードやデータを使って説明することで、内容の質が高まります。
2. 構成(Organization)
英作文の構成は、文章の流れや論理性を評価する重要な要素です。以下のポイントに注意しましょう:
序論、本論、結論の明確な区別:英作文には、序論(Introduction)、本論(Body)、結論(Conclusion)の3つの部分が必要です。序論では、主題や目的を簡潔に述べ、本論で詳細な議論を展開し、結論で要点をまとめるとよいでしょう。
段落ごとの一貫性:各段落は一つの主題に絞り、その主題を中心に展開する必要があります。段落が論理的につながっていることも評価されます。例えば、アメリカでの生活についてのエッセイであれば、一つの段落では住居事情について述べ、次の段落では交通手段について触れる、といった流れが一つの例になります。
論理的なつながり(Coherence):文章全体の流れが自然であり、各段落が互いに関連していることが重要です。適切な接続詞(for example, however, in addition など)を使って、文と文、段落と段落のつながりを意識すると、読み手にとって理解しやすい文章になります。

3. 語彙(Vocabulary)
語彙の評価は、使用されている言葉の豊かさと適切さに基づいて行われます:
幅広い語彙の使用:同じ単語を繰り返すのではなく、さまざまな表現を使うことが求められます。特に、アカデミックな英作文では、専門用語や抽象的な概念を説明するための言葉が適切に使われているかが重要です。例えば、"good"や"bad"の代わりに、"beneficial"や"detrimental"といった言葉を使うと、より洗練された印象を与えることができます。
文脈に合った語彙の選択:使われている言葉がその文脈にふさわしいかも評価対象です。例えば、カジュアルなエッセイでは"kids"でも問題ありませんが、フォーマルなアカデミックエッセイでは"children"を使用するのが一般的です。
スペルミスの少なさ:スペルミスやタイプミスは、評価を下げる原因となるので、十分に注意しましょう。
4. 文法(Grammar)
文法の評価では、文法構造の正確さや多様さがチェックされます:
文法の正確さ:基本的な文法ミス(主語と動詞の一致、冠詞の使い方、前置詞の使い方など)が少ないかどうかが評価されます。文法の正確さを保つことで、読み手にとって信頼性の高い文章となります。
さまざまな文法構造の使用:単純な文だけでなく、複合文や従属節を含む複雑な構造を使いこなすことが重要です。例えば、"I think that…"という構文だけでなく、"It is often argued that…"や"Considering the fact that…"といった表現を取り入れると、評価が高まります。
カンマ、ピリオドの使い方:正しいカンマ、ピリオドの使用も重要な要素です。英作文の採点基準を徹底解説!内容、構成、語彙、文法のポイントとは?句読点の誤りは、文章の意味を誤解させる可能性があるため、特に気をつけましょう。
まとめ
英作文の採点基準である「内容」「構成」「語彙」「文法」の4つのポイントを理解することは、高評価を得るための第一歩です。アメリカでの駐在、在住、留学生の皆さんも、これらの基準を意識して英作文の練習に取り組むことで、より質の高い文章が書けるようになっていきます。英作文は、表現力を高めるための重要な手段であり、コミュニケーションスキル向上にも役立つので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。
記事作成者 (Manami Palmini)  講師経歴
過去のサポート歴
|