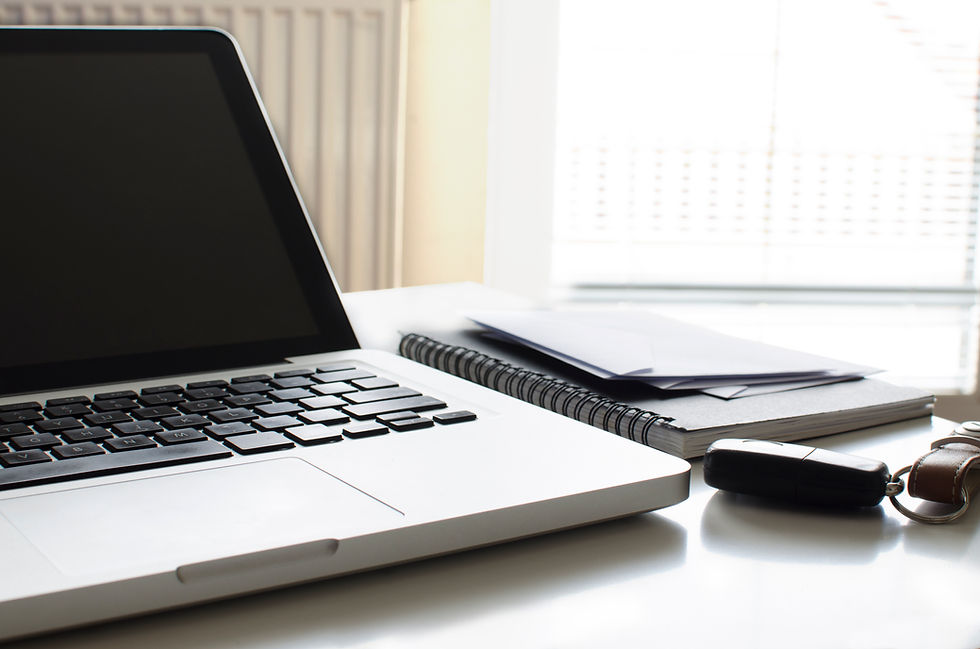英検・英作文で差がつく!ボディパラグラフの書き方
- Manami
- Oct 17, 2025
- 6 min read
英検や学校の英作文、留学の出願用エッセイを書くとき、文章全体の構成力はとても大切です。
その中でも、ボディパラグラフ(本文部分)は、読者にあなたの考えを具体的に伝える「心臓」のような部分です。
導入で示した意見を支え、説得力のある文章にするのが役割です。
今回は、英検やエッセイで役立つボディパラグラフの書き方を、具体例を交えながらわかりやすく紹介します。

① まずはトピックセンテンスをはっきりさせる
ボディパラグラフの最初には、「この段落で何を伝えるのか」を一文で示すトピックセンテンスが必要です。
これによって、読者はこれから書かれる内容を理解しやすくなります。
例えばこんな感じです。
Online education provides more learning opportunities for students around the world.(オンライン教育は、世界中の学生により多くの学びの機会を提供しています。)
この一文で、「オンライン教育の利点」について書く段落だと分かります。
トピックセンテンスは、簡潔で意見が明確であることがポイントです。
② 理由や根拠をしっかり示す
トピックセンテンスで主張を示したら、「なぜそう思うのか」を説明します。
英検やエッセイでは、理由や根拠をきちんと示すことが高評価につながります。
先ほどの「オンライン教育」の例なら、こう書けます。
Many students who live in rural areas or developing countries can now access high-quality education through online platforms.(地方や発展途上国に住む多くの学生が、オンライン学習を通して質の高い教育にアクセスできるようになっています。)
According to UNESCO, online learning has increased global access to education, especially after the COVID-19 pandemic.(ユネスコによると、オンライン学習は特にコロナ禍以降、世界中の教育の機会を広げているそうです。)
このように、データや調査結果を簡単に紹介することで、文章に説得力が生まれます。
③ 具体例を使ってわかりやすくする
理由や根拠だけだと少し抽象的です。
そこで、具体例や体験談を加えると、読者にイメージしやすくなります。
For example, a high school student in India was able to take computer science courses from an American university through online programs.(例えば、インドの高校生がオンラインを通じてアメリカの大学のコンピュータサイエンスの授業を受けられたそうです。)
This experience allowed her to learn advanced technology that was not available in her local school.(この経験を通して、地元の学校では学べなかった先端技術を学ぶことができました。)
また、自分の体験を入れるとオリジナリティも出せます。
When I took an online English course, I could interact with teachers from different countries, which made me more confident in speaking English.(私がオンライン英語コースを受けたとき、いろいろな国の先生と話すことで、英語を話す自信がつきました。)
短い英作文でも、自分の経験を加えると文章が自然で説得力のあるものになります。

④ 文と文のつながりを意識する
ボディパラグラフでは、文と文のつながりも大切です。
文章がバラバラだと、読者が内容を理解しにくくなります。
接続語を使うと、文章の流れがスムーズになります。
用途 | 代表的な接続語 | 日本語の意味 |
追加 | moreover, in addition, also | さらに、そのうえ |
例示 | for example, for instance | 例えば |
対比 | however, on the other hand | しかし、一方で |
結果 | therefore, as a result | その結果 |
強調 | in fact, indeed | 実際に、確かに |
例文:
Online education is convenient and accessible. Moreover, it allows students to learn at their own pace.(オンライン教育は便利でアクセスしやすいです。さらに、自分のペースで学ぶこともできます。)
このように接続語を使うだけで、文章が自然に繋がります。
⑤ 前後の段落との関係も意識する
ボディパラグラフは独立しているようで、前後の段落とつながる必要があります。
例えば、1つ目のパラグラフでオンライン教育の利点を述べたなら、次のパラグラフでは課題や改善策を書くと自然です。
While online education has many benefits, it also presents challenges such as lack of communication and motivation.(オンライン教育には多くの利点がありますが、コミュニケーション不足ややる気の低下といった課題もあります。)
こうすることで、エッセイ全体の流れがスムーズになり、読みやすくなります。
実際に書いてみよう:ボランティア活動の例
では、ここまでの流れを使って、ボディパラグラフを1つ作ってみます。
テーマは「ボランティア活動の大切さ」です。
トピックセンテンス
Volunteering plays a vital role in building stronger communities.(ボランティア活動は、より強い地域社会を作るうえで大切です。)
理由と具体例
Through volunteer work, people learn to cooperate and develop empathy for others.(ボランティア活動を通して、人は協力する力や他者への共感を育むことができます。)
For instance, when I volunteered at a local food bank, I met many people who were struggling financially.(例えば、地元のフードバンクでボランティアをしたとき、経済的に困っている多くの人に出会いました。)
This experience taught me the importance of helping others and made me more aware of social issues.(この経験を通して、人を助けることの大切さを学び、社会の問題にも気づくことができました。)
次の段落へのつなぎ
Therefore, schools and communities should encourage young people to participate in volunteer programs.(ですから、学校や地域は若者がボランティアに参加できるよう支援すべきです。)
このように、「トピックセンテンス → 理由 → 具体例 → まとめ」の順番で書くと、ボディパラグラフが読みやすく、説得力のある文章になります。
まとめ
ボディパラグラフは、英検やエッセイで最も重要な部分です。書くときのポイントは以下の通りです。
トピックセンテンスで段落の主張を明確にする
根拠や理由を示す
具体例や自分の体験でイメージを具体化する
接続語で文の流れを自然にする
前後の段落とのつながりを意識する
これらを意識することで、文章全体が論理的でわかりやすくなります。
英検の英作文でも、読者が読みやすく納得できる文章を書くことは高得点につながります。
まずは小さな例から練習し、徐々に複数のパラグラフを組み合わせることで、説得力のあるエッセイを書けるようになります。
記事作成者 (Manami Palmini  講師経歴
過去のサポート歴
|