英作文や面接に正解はない? 子どもに必要な“問いに向き合う力”とは
- Manami
- Jul 4, 2025
- 5 min read
「正解を教えてください」
「この答えでいいですか?」
これは、英語教育の現場や帰国子女受験の面接練習で、子どもたちからよく聞かれる言葉です。
アメリカに住むお子さんを指導していてもよく聞かれます。
たとえば英作文の練習で「あなたはペットを飼いたいですか?」という問いを出したとき、返ってくるのは
「どっちが正解なんですか?」
「Yesですか?Noですか?」
という反応。
また、帰国子女枠の面接対策でも、「この質問にはどう答えるのがいいですか?」という「模範解答」を求める姿勢が目立ちます。
でも、そもそも正解はないのです。
答えが一つではない問いにどう向き合うか。
そこでこそ、子どもたちの「思考力」や「自分で考える力」が育つチャンスがあります。
この記事では、「正解がない問い」がなぜ今の子どもたちにとって重要なのか、英作文や帰国子女受験を例にしながら、これからの学びに必要な考え方を紐解いていきます。
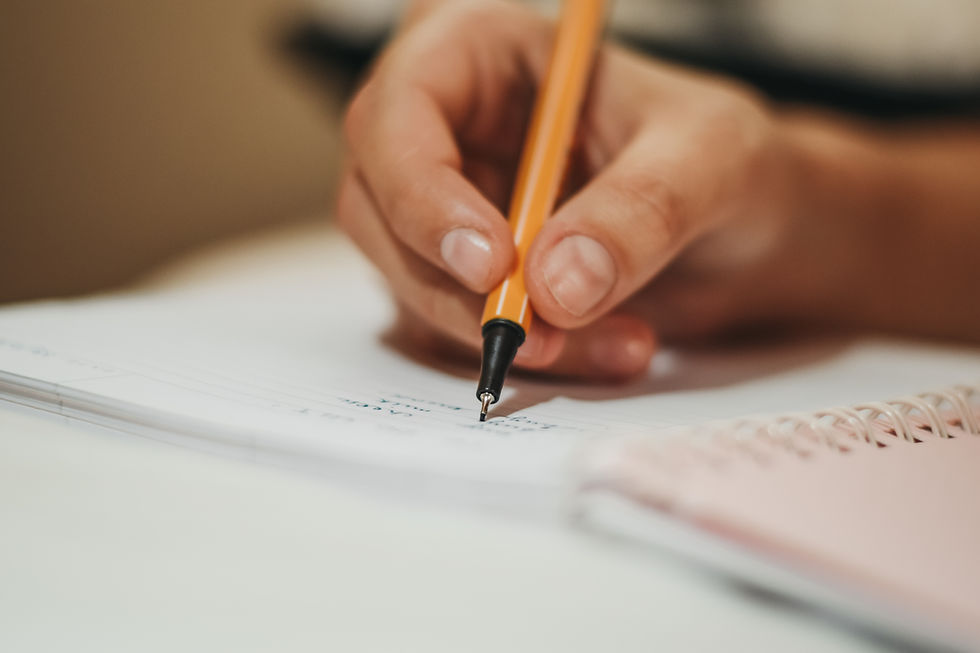
英作文や面接には「正解」が存在しない
まず、英検の英作文や、帰国子女受験の面接を思い浮かべてみてください。
問われるのは、
「あなたは〇〇についてどう思いますか?」
「なぜそう考えますか?」
といったオープンエンド型の問いです。
このような問いに、絶対的な正解はありません。
YesでもNoでも、それを選んだ理由がしっかりしていれば、どちらでも構わないのです。
でも多くの子どもたちは、「どちらが先生にとって“嬉しい”答えか?」を探してしまいます。
つまり、「評価されそうな答え」を予想して、それに自分を合わせようとするのです。
それは長年、「正解のある問い」に慣れてきた学習スタイルの副作用とも言えるかもしれません。
なぜ「正解がない問い」は子どもを戸惑わせるのか
学校教育では、多くの問いに正解があります。
算数の計算問題、理科の用語、社会の年号。
「これが正しい」「これが正解」と教えられて育った子どもたちは、それ以外の答え方に戸惑ってしまいます。
でも、現実の社会には「これが正しい」と一言で言えない問題がたくさんあります。
SNSは子どもに良い影響を与えているか?
ロボットやAIが仕事をすることにどう思うか?
勉強と遊び、どちらが大切か?
こういったテーマに「唯一の正解」などありません。
答えはその子の考え方や経験によって変わりますし、そこにこそ「表現力」「思考力」「人間性」がにじみ出ます。
「教えられない問い」に、どう向き合うか
英作文や面接で子どもに「どう答えたらいいの?」と聞かれたとき、私はこう答えるようにしています。
「私は答えを持っていないよ。でも、あなたの答えは何?」
そう言うと、子どもたちは最初は戸惑います。
でも少しずつ、「自分の答えは何だろう」と考え始めます。
そして、「えっと…私はこう思うかもしれない」と、恐る恐る自分の考えを口にし始めるのです。
この「自分で考える」プロセスこそが大切です。
イエスかノーでは終わらない世界へ
これからの時代、子どもたちが向き合っていく社会は、白黒はっきりしない問いの連続です。
テクノロジーの進化は本当に幸せをもたらすのか?
環境問題と経済成長、どちらを優先すべきか?
誰かの「正義」は、他の人にとっても「正義」なのか?
こうした複雑な問題に対して、Yes/Noの二択で答えることはできません。
自分で考え、自分の中でバランスをとりながら、「自分なりの答えをつくる力」が求められます。
それは英作文の練習の中でも、面接の練習の中でも、少しずつ育てていける力です。
思考力は「経験」から育つ
「自分の考えを持ちましょう」と言われても、子どもたちはすぐには答えられません。
それは、考えがないからではなく、「考える訓練をしてこなかった」から。
思考力は、与えられるものではなく、経験から育てるものです。
自分の言葉で話してみる
友だちや先生と意見を交換してみる
答えが出ない問いに向き合ってみる
間違っても大丈夫と感じられる環境で考える
そうした積み重ねが、「自分の頭で考えることは面白い」と思えるきっかけになります。

帰国子女受験や英検で問われている力とは?
帰国子女枠の面接や英検の二次試験で、最も評価されるのは「思考の深さ」と「表現の明確さ」です。
英語力そのもの以上に、「自分はこう思う」「その理由はこうだ」と根拠を持って語る力が求められています。
英語でのコミュニケーションは、言葉だけでなく、「何を伝えたいか」が明確であることが前提です。
だからこそ、「正解を探す姿勢」から、「自分で考える姿勢」への転換が必要なのです。
大人ができるサポートは「問いを共有すること」
子どもたちが「正解のない問い」に向き合うとき、大人にできるのは「答えを教えること」ではありません。
むしろ、「一緒に考えること」「問いそのものを面白がること」です。
「あなたはどう思う?」と問い返してみる
「その考え、面白いね」と受け止めてみる
「もう少し詳しく説明してみて」
「自分だったらこう思うかも」と意見を交換してみる
そうした日々のやりとりが、子どもたちにとっての「思考の土台」となります。
まとめ:「正解がない問い」こそ、未来への準備
今の子どもたちにとって、最も大切な力は「正解を言うこと」ではなく、「自分で問いを立て、自分なりの答えをつくること」です。
英作文でも、面接でも、それははっきり表れています。
模範解答の丸暗記ではなく、自分の経験や感情から生まれる「自分だけの答え」を言葉にすること。
それこそが、これからの時代に必要とされる、本当の意味での「学びの力」となっていくでしょう。
子どもたちが、答えのない問いに出会ったとき、どうか「困った」ではなく、「面白い」と感じられるように。
私たち大人ができるのは、一緒に考えるという視点をもつことだと信じでいます。
記事作成者 (Manami Palmini  講師経歴
過去のサポート歴
|




